「ホロライブ」――今や世界中のファンを魅了するVTuberグループとして、その名を知らない人はいないでしょう。多くの人が憧れ、夢見るこの場所への扉を開くためには、一体何が必要なのでしょうか?今回は、ホロライブプロダクション所属のVTuber、儒烏風亭らでん氏が語る、そのあまりにもユニークで波乱万丈なオーディション体験談を紐解き、私たち一般的な社会人の視点から、その合格の秘訣と、夢を追いかける上で大切な心構えを探っていきたいと思います。
らでん氏の体験談は、一般的なオーディション対策の常識を覆すような、まさに「型破り」なエピソードの連続です。しかし、その根底には、目標に向かってひたむきに努力する姿勢と、自身の「個性」を最大限に活かす戦略が見え隠れします。この記事を通じて、ホロライブを目指す方々はもちろんのこと、何か大きな目標に挑戦しようとしているすべての方々に、新たな視点と勇気をお届けできれば幸いです。(この記事はいち個人である私自身の考え、見解をまとめたものです。皆さんの一つのヒントになれば嬉しいです。)
疑念から始まった道のり:情報収集の重要性と、その「落とし穴」

ホロライブオーディションへの挑戦は、らでん氏にとって意外な形で幕を開けました。書類選考を通過したとの連絡を受けた際、彼女が抱いたのは

「詐欺やと思ったっちゃ」(原文ママ)
という率直な感想だったそうです 。このような連絡が突然舞い込んできた場合、多くの人がまず疑ってしまうのは無理もありません。夢のような話は、往々にして現実離れしていると感じられるものです。しかし、らでん氏はその「詐欺」を疑いつつも、「尻尾捕まえて悪を成敗!」というような気持ちで、正式なものかどうかを見極めようとしたといいます。結果としてそれが本物だと判明した時、彼女は覚悟を決め、ホロライブ合格に向けて真剣な努力を始めます。
その努力の一環として、らでん氏は



「ホロライブのことを一生懸命頑張って調べてた」 (原文ママ)
そうです。現代において、何かを成し遂げる上で情報収集は不可欠です。特に、過去の成功例や経験者の声は、具体的な対策を練る上で非常に貴重な手がかりとなります。彼女は、ホロライブの先輩である大空スバル氏の過去の配信の中に、ホロライブオーディションに関する情報を見つけ出します。そこで語られていたのは、「ダンスと歌のテストあるんですか?」という問いに対して、「無いです。特にスバルも受けた記憶は特にないです。」という明確な回答でした 。
歌が苦手だったらでん氏にとって、この情報はまさに救いの手でした。彼女は、



「らでん、お歌が苦手やけんが、お歌関係のことを聞かれたら積むなっていうの」 (原文ママ)
という不安を抱えていたため、



「歌唱オーディションはありませんって言っとったちゃね。良かった歌唱オーディション無いんだなと思って、あー良かった良かった良かった良かった。これでね安心して、あの面接に望めるわってことでございまして。」 (原文ママ)
と、安堵のため息をついたといいます。
私たち一般的な社会人の感覚からしても、苦手な分野のテストがないというのは、これほどまでに心強い情報はありません。事前準備の方向性が明確になり、自身の強みに集中できると考えれば、これほど効率的な話はないでしょう。らでん氏のこの情報収集と、それに基づく準備の姿勢は、どんな目標に対しても模範となる行動だと言えます。しかし、彼女の体験談は、ここから予想もしない展開を迎えることになります。情報収集は重要ですが、それが常に最新であるとは限らない、という教訓を私たちに示唆しているかのようです。
予期せぬ試練:歌唱オーディションの勃発と、絶体絶命の危機


事前の情報収集で「歌唱オーディションはない」と知り、安心しきって面接に臨もうとしていたらでん氏を待ち受けていたのは、まさに青天の霹靂でした。何度目かの面接の際に届いた次の連絡は、



「次の面接では歌唱オーディションがあります。※※日後に、歌唱オーディションをやります。」 (原文ママ)
というものだったのです。この知らせに、らでん氏は



「待って待って待ってだって無いって無いって、え嘘?みたいな。か、か、歌唱オーディション?え?しかも本当のガチの歌唱オーディションで、面接をしながら、あじゃあこれ歌ってみてくださいみたいなやつじゃなくて、もう歌だけ。うん、歌だけ聞かせてください。のオーディションやったちゃん」 (原文ママ)
と、パニックに陥った様子を語っています。
これは、私たち社会人がプロジェクトや業務を進める中で、計画が急に変更されたり、予期せぬ課題が発生したりする状況と非常に似ています。それまで積み上げてきた準備が、一瞬にして意味をなさなくなるような感覚です。らでん氏は、この状況の変化を



「スバル先輩嘘つき!ていうあれではなく、決してそういうあれではなく、状況が変わったんだなっていうぐらいに聞き流してもらえばいいちゃけど」 (原文ママ)
と、冷静に受け止めています。これは彼女の成熟した姿勢を示しており、他者を責めるのではなく、状況を客観的に判断しようとする冷静さがあったからこそ、次の一手へと繋げられたのだと感じます。
苦手な歌で、しかも「歌だけを聞かせる」という本格的なオーディション。準備期間も限られている中で、らでん氏の置かれた状況はまさに絶体絶命でした。多くの人がここで諦めてしまってもおかしくありません。しかし、彼女は



「ここまで来たら、らでんも受かりたいって思うわけでございますよ」 (原文ママ)
と、強い意志を胸に、この困難に立ち向かうことを決意します。この「何としてでも合格したい」という強い気持ちこそが、彼女を次の行動へと駆り立てる原動力となったのです。私たちも、仕事や人生の目標において、困難に直面した時に「本当にこれを成し遂げたいのか」という自身の内なる問いに向き合うことが、突破口を開く鍵となるのではないでしょうか。
窮地を救った知人の助け:基礎と心の重要性
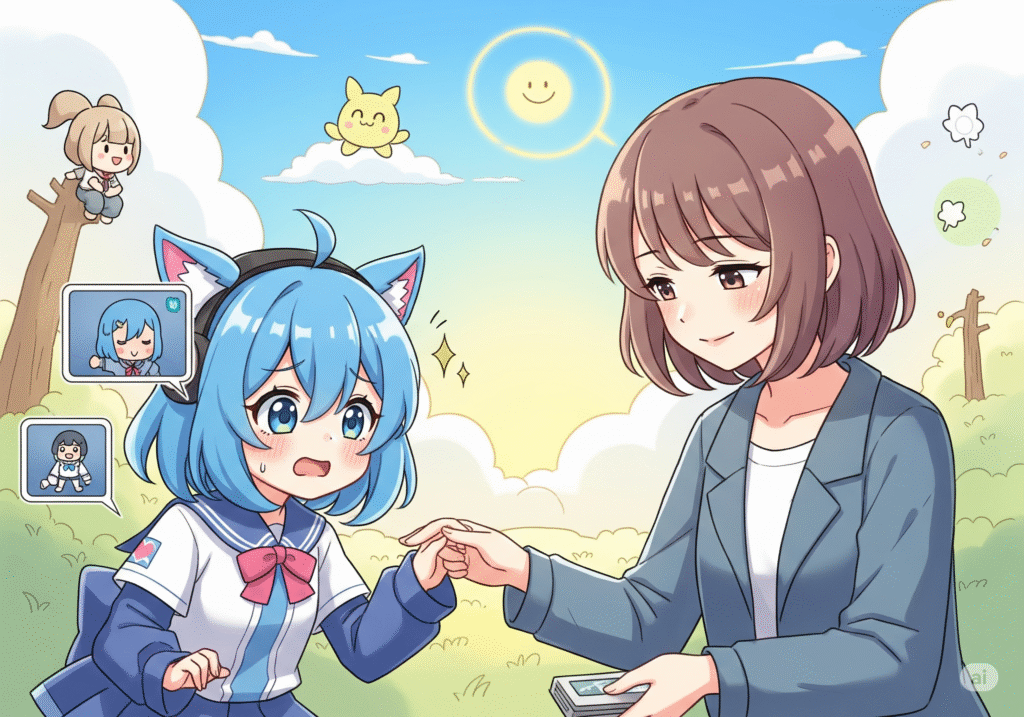
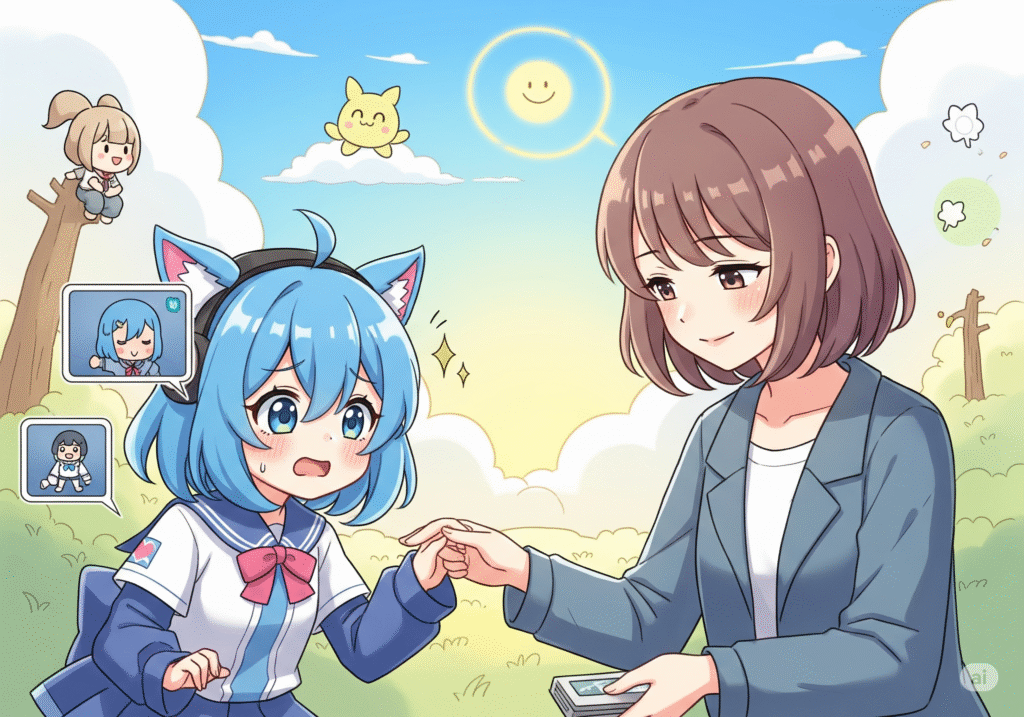
歌唱オーディションの知らせを受け、窮地に立たされたらでん氏がとった行動は、非常に戦略的であり、同時に人間関係の温かさを感じさせるものでした。彼女は「すごく歌がうまい知人」に助けを求めます。しかし、ホロライブのオーディションであることは機密情報であり、詳細を明かすことはできません。そこで彼女は、相手に何の事情も説明できないまま、



「歌を教えてくれないか。マジでちょっと、本当に事情は何も言えない。本当に何も言えなくて申し訳ないんだけど、何も聞かずに歌を教えてくれないかって言ったちゃ」 (原文ママ)
と、非常に切羽詰まった状態で頼み込んだといいます。
この依頼は、受け手からすれば非常に不可解で、通常であれば断られても仕方がないような状況です。しかし、その知人は



「心良く、あいいよ。みたいな軽い感じ。あいいよ、分かったっつって」 (原文ママ)
と、快く引き受けてくれたそうです。このエピソードは、日頃からの人間関係の構築がいかに大切か、そして、本当に困った時に手を差し伸べてくれる友人の存在がどれほど心強いかを物語っています。私たち社会人も、専門分野で助けが必要な時や、精神的に支えが必要な時など、日頃からの信頼関係が重要な局面で活きてくることを改めて教えてくれます。
残された短い時間の中で、知人がらでん氏に施した歌の指導は、非常に理にかなったものでした。知人は、



「コテ先のテクニックみたいなのは、こう、何やったところでバレると」 (原文ママ)
と見抜き、小手先の技術ではなく、



「本当に基礎的な声を出るようにする。みたいな所と、後は何かちょっと、あの歌に遅れない(音源に)」 (原文ママ)
という、つまり



「発声っていう所と、あと遅れないっていう所、もうこの二つ だけやって行こう」 (原文ママ)
という、基本中の基本に絞った指導を行ったのです。短期間での上達を目指す上で、最も重要な要素に集中するというこのアプローチは、仕事においても「パレートの法則」のように、成果に直結する2割の要素に集中することの重要性を示唆しています。
さらに、知人は技術面だけでなく、精神面でのアドバイスも与えました。彼女の長所を「元気なところ」と見抜き、



「もうとりあえず、元気に歌えって。もうその場を楽しんで歌えと。なんならその場を、もう自分のステージだと思って歌えって言われたっちゃ」 (原文ママ)
と励ましました。このアドバイスは、技術が未熟であっても、いかにその場の雰囲気を楽しみ、自分らしく表現するかが、聴衆に感動を与える上で重要であるかを教えてくれます。オーディションやプレゼンテーションなど、人前で自分を表現する機会において、完璧な技術よりも、その人が持つエネルギーや情熱が評価されることは多々あります。知人は



「友人は、何かカラオケ大会か何かだと思ってるんでしょうね」 (原文ママ)
と、らでん氏の秘密を知らないまま、最高のコーチングをしてくれたのです。
らでん氏は、この指導を受けて



「その歌手オーディションまでとにかく発声だけをやり続ける」 (原文ママ)
という努力を続けます。そして、



「出来ることはやったでって」 (原文ママ)
と本番に臨みました。この、たとえ完璧でなくとも「やれることは全てやった」という自己肯定感は、プレッシャーの高い状況で最高のパフォーマンスを発揮するために不可欠なものです。
極度の緊張と「喋り」の封印:自身の弱点と向き合い、乗り越える


歌唱オーディション当日、らでん氏が経験したのは「極度の緊張」でした。彼女は



「もう、そんなん人前で歌った事なんてないし」 (原文ママ)
と語り、自身の強みと弱みを冷静に分析していました。



「儒烏風亭らでんは、もう喋りしかないわけよ。ゲームもでき ない、歌も歌えない喋りしかない。」 (原文ママ)
と、普段の彼女を知るファンにとっては驚きの告白です。彼女にとって、歌はまさに自身の「弱点」であり、唯一の武器である「喋り」が封印された歌唱オーディションは、



「もう儒烏風亭らでん、どうしようもないと」 (原文ママ)
と感じるほどの試練だったのです。
私たち社会人も、得意な分野では饒舌に話せても、不慣れな場では途端に口数が減ったり、自信を失ったりすることがあります。自分の「十八番」が使えない状況で、どう立ち振る舞うかは、プロとしての真価が問われる場面です。らでん氏は、そんな心臓が破裂しそうなほどの緊張の中、



「心臓バクバクのまま歌唱オーディション終えた」 (原文ママ)
と語っています。この経験は、彼女が自身の弱点と真摯に向き合い、それを乗り越えようとする強い精神力を持っていたことを示しています。結果として彼女は



「無事通過いたしまして。」 (原文ママ)
と、この難関を突破しました。この成功は、完璧を目指すのではなく、与えられた状況で最善を尽くすこと、そして何よりも「諦めない」心の重要性を教えてくれます。知人への感謝を



「本当にありがとうって言いたいね。言えないけど。うん何も言えないけど、あの、ありがとうってすっごい思ってます」 (原文ママ)
と語る彼女の言葉からは、支えてくれた人への深い感謝と、秘密を抱える立場としての葛藤が垣間見え、非常に人間味あふれる一面を感じます。
予想外の「フリートーク」:禁断の話題と奇跡の通過


歌唱オーディションの突破は、決してゴールの意味ではありませんでした。らでん氏のホロライブオーディションは



「歌唱オーディションを経て、ま、さらに色々話さなければならないんですよ」 (原文ママ)
と続き、しかも



「3日後に、じゃあこれやりますよ。それ終わってじゃあ3日後にこれやりますよ。みたいな結構ね時間がない中で」 (原文ママ)
と、短期間で複数の面接が立て続けに行われたようです。このような状況下では、冷静さを保ち、臨機応変に対応することが非常に難しくなります。彼女も



「オーディションってね、やっぱりちょっと若干緊張する訳よ 。やからね、その引き出しを事前に整理しとったとしても、あれこれ何どこやったっけ?みたい。どの引き出し開けるんやったっ け?みたいな。」 (原文ママ)
と、パニック状態に陥ったことを明かしています。
そして、そのパニックの最中、



「フリートークしてくださいっていう質問」 (原文ママ)
が投げかけられた時、らでん氏は信じられないような選択をします。



「街中でよく、あの男性像のブロンズ 彫刻とかあるじゃないすか。あのブロンズ 彫刻、次見た時に、あの是非股間の方を注視 して見て頂きたいんですけれども。ていう話から始まって」 (原文ママ)
と、まさかの下ネタを切り出したのです。その内容は、公共の場にある男性像の彫刻の股間部分が



「抽象的に掘られてるわけよ。こう、ふわってふわって掘られとるわけよ。これ何でかて言うとね、あの厳密に掘ってしまうと苦情が来るからですね。」 (原文ママ)
という、非常に学術的な(?)解説から、



「曖昧もっこり、がははっつって曖昧もっこり。これが股間の男性 のシ・・・ 股間和歌集、何つってガハハっていう話よね。」 (原文ママ)
という、ある意味センセーショナルなキーワードまで飛び出しました。
この「股間和歌集」という言葉が、実は木下直之氏の文献に登場する正式な学術用語であると補足するあたり、らでん氏の教養の深さには驚かされます。しかし、オーディションという場でこのような話題を出すのは、私たち社会人の感覚からすれば、まさに「タブー破り」です。彼女自身も



「落ちたな、と思いましたね。その話した時に、あ、これは落ちたなと。ああもう落ちた落ちた。仕方ねえやと思っていたら」 (原文ママ)
と、不合格を確信したといいます。しかし、驚くべきことに、その結果は



「まさかの落ちてませんでしたね、びっくりしました皆 さん」 (原文ママ)
というものでした。
このエピソードは、オーディションや採用面接の常識を根底から覆すものです。一般的には、品位や協調性が重視される場で、このような「攻めた」話題を出すことはご法度とされています。しかし、らでん氏の場合はそれが



「だいぶそれが受けたようで」 (原文ママ)
と、まさかの高評価に繋がりました。これは単に下ネタが面白かった、という話ではなく、彼女の持つ「知的な好奇心」「ユニークな視点」「窮地でパニックになりながらも、自分をさらけ出す勇気」といった、他にはない個性が、面接官に強く響いた結果ではないでしょうか。型にはまらない「自分らしさ」を貫くことの重要性を、これほどまでに雄弁に語るエピソードは他にありません。
味を占めた?:さらなる攻めのフリートークと、成功の要因


一度「攻めた」話題が奏功したことを経験したらでん氏は、その後もその路線を続けます。



「味を占めた儒烏風亭らでんは、え、その次の面接で、あのなんて言うんですかねえ、ま、おっぱいの話をしましたね。」 (原文ママ)
と、さらに際どい話題に挑戦したといいます。しかし、これも単なる下ネタではありませんでした。彼女は



「美術史の表現において、おっぱい1 個だけ見てもすごいすよっ つって。ま、そのおっぱいの表現 から見る、あの何ちょっとえ西洋絵画と日本絵画の違いみたいな、あの線による表現と影による表現がですねこれ違うんですね、みたいな。」 (原文ママ)
と、今回もまた、その話題を知的な視点から深掘りしました。
この「おっぱいの表現から見る西洋絵画と日本絵画の違い」というテーマは、一見すると際どいながらも、美術史という専門知識に裏打ちされた非常にユニークなトークテーマです。らでん氏は、単に話題のインパクトを狙うだけでなく、そこに知的な深みと彼女自身の興味関心、そして観察眼を織り交ぜていました。私たち社会人も、プレゼンテーションや会議の場で、聞き手の興味を引きつける「フック」となる話題は非常に重要だと感じます。しかし、そのフックだけで終わらず、自分の専門性や深みのある知識へと繋げることで、聞き手に「この人は面白いだけでなく、確かな知識と視点を持っている」という印象を与えることができます。らでん氏は、まさにその成功例を示してくれたと言えるでしょう。
未来のホロメンへ:普遍的な教訓
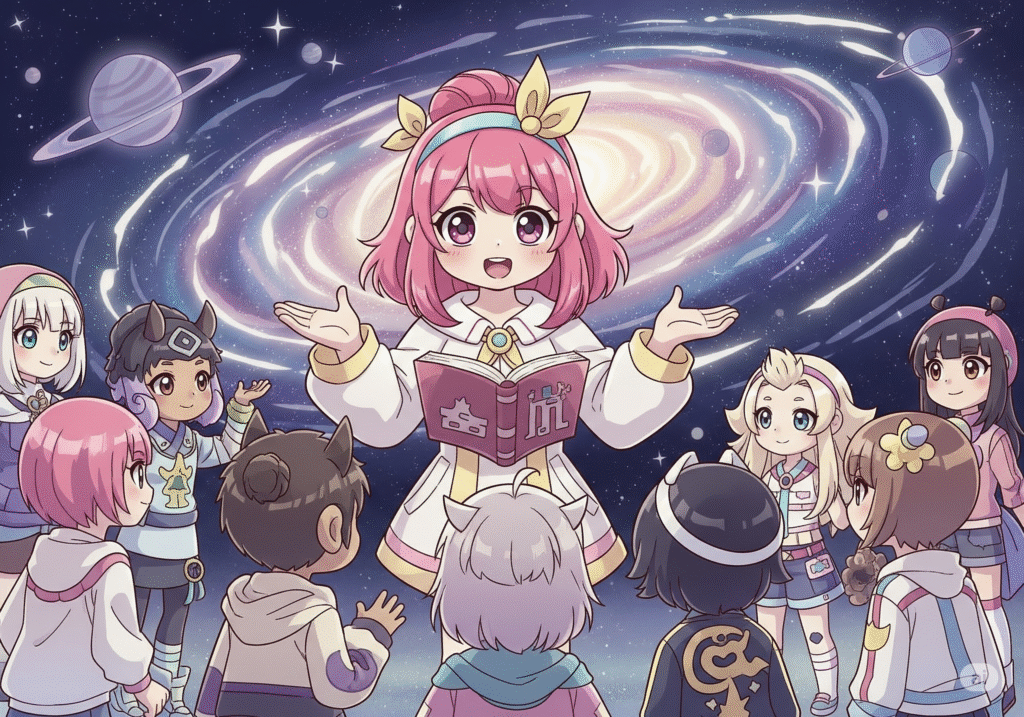
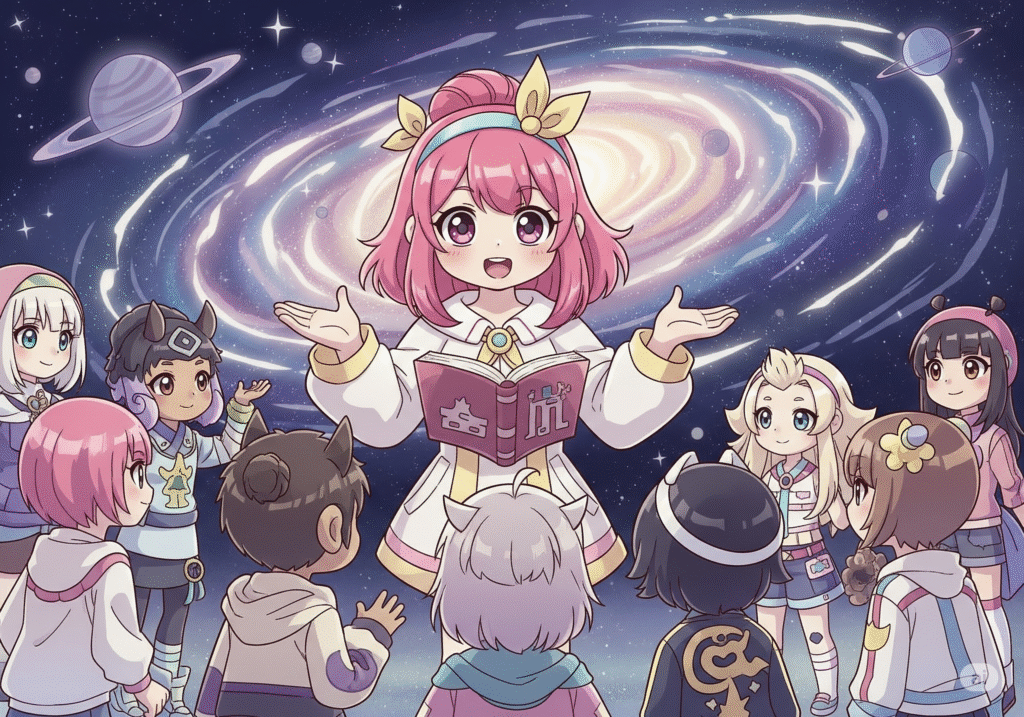
数々の波乱に満ちたオーディションを乗り越え、ホロライブのメンバーとなった儒烏風亭らでん氏。彼女は最後に、これからホロライブオーディションを受けようとする人々へ、重要なメッセージを送っています。それは



「下ネタを話せば受かるというわけではございません」 (原文ママ)
という、非常に冷静かつ現実的な忠告です。
この言葉は、彼女の体験談が特殊な例であることを示唆するとともに、表面的な模倣では成功できないという普遍的な真理を突いています。らでん氏の合格は、下ネタを話したからではなく、彼女がその状況下で「自分らしく」あり、「知的好奇心」と「ユニークな発想」、そして「どんな困難にも立ち向かう強い意志」を見せた結果だと解釈すべきでしょう。
彼女の体験談から、私たちは以下のような普遍的な教訓を学ぶことができます。
1. 情報収集と適応力: 事前の情報収集は重要ですが、それが全てではありません。状況は常に変化し得るものであり、それに柔軟に対応できる適応力が求められます。計画通りにいかない時こそ、真価が問われるのです。
2. 人脈の力と感謝: 困った時に助けを求められる信頼できる人脈は、かけがえのない財産です。そして、助けてもらった恩を決して忘れない感謝の心は、人間関係を豊かにします。
3. 基礎力の徹底: 時間がない中でも、小手先のテクニックに走らず、基礎を徹底的に固めることが、最終的なパフォーマンスの向上に繋がります。どんな分野においても、基本を疎かにしない姿勢が大切です。
4. 個性の発揮と自己受容: 自分の弱点を受け入れつつ(歌が苦手)、得意なこと(喋り)を活かすのはもちろん、時には「パニックの中で出た言葉」のような予期せぬ個性も、あなただけの魅力になり得ます。重要なのは、ありのままの自分を表現し、それを信じることです。
5. 逆境を乗り越える精神: 苦手な歌唱オーディションに直面しても、極度の緊張の中でも、「何としてでも受かりたい」という強い意志を持って挑むこと。困難な状況を乗り越えようとするその姿勢こそが、道を開きます。
6. 諦めない心と前向きな姿勢: 「落ちたな」と思っても、結果が出るまでは諦めないこと。そして、結果を受け止め、次の行動へと繋げる前向きな姿勢が、未来を切り開きます。
まとめ:夢を掴むために、あなただけの「色」を見つけよう
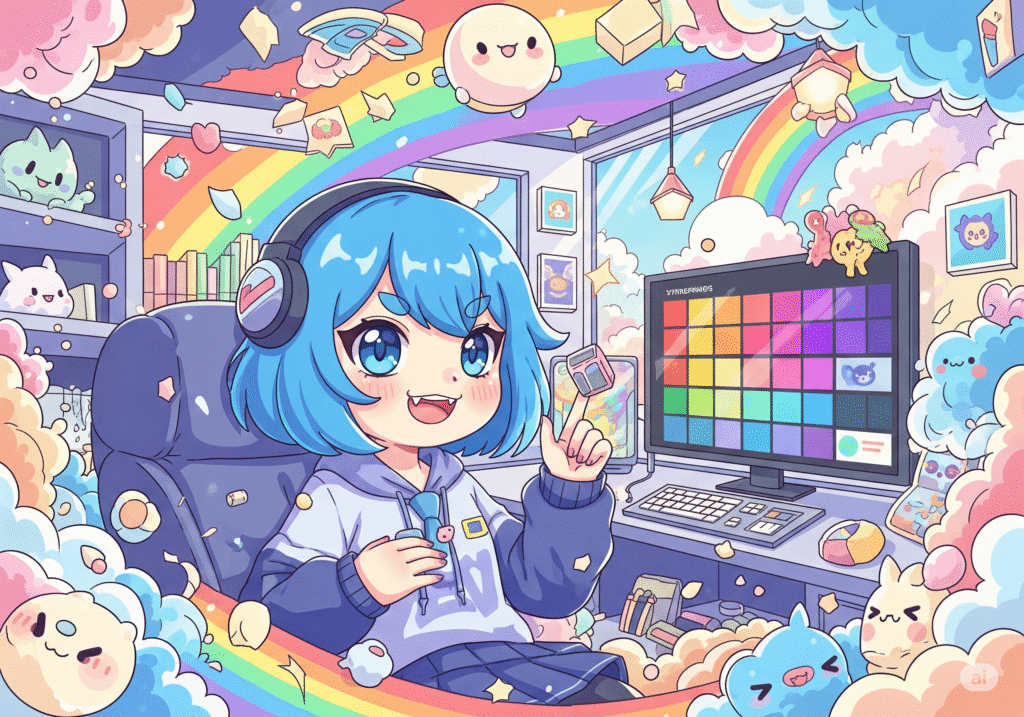
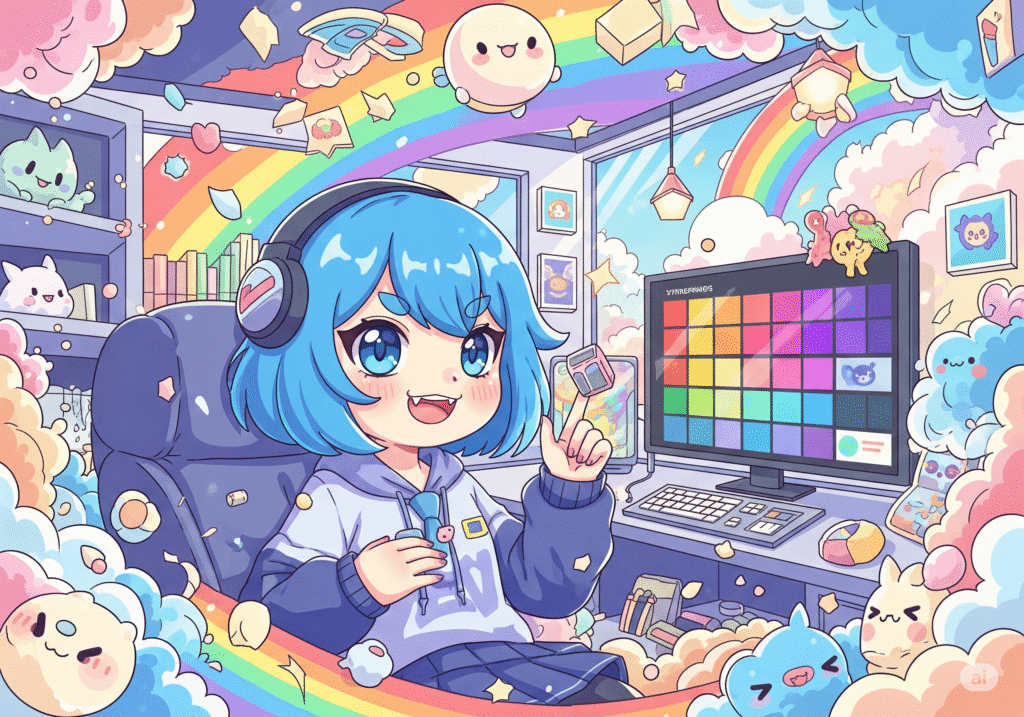
儒烏風亭らでん氏のホロライブ合格への道のりは、まさに波乱万丈、予測不能なものでした。彼女の体験談は、一般的なオーディション対策書には書かれていない、しかし非常に本質的な「夢を掴むためのヒント」が詰まっています。それは、情報に盲目的に従うのではなく、自身の置かれた状況を冷静に分析し、時に大胆な行動に出る勇気を持つこと。そして何よりも、自身の「個性」を最大限に信じ、それを恐れることなく表現することの重要性です。
私たちは皆、それぞれ異なる個性や強み、そして弱点を持っています。らでん氏が「股間若衆」や「おっぱい談義」を通じて自身の知的好奇心とユニークな視点を表現したように、あなたにも、あなただからこそ語れる「特別な何か」があるはずです。完璧な人間になろうとするのではなく、あなた自身の「色」を見つけ、それを恐れずに表現する勇気を持つこと。それが、ホロライブに限らず、どんな分野においても、あなたの夢を現実にするための鍵となるでしょう。
挑戦する道のりには、必ず困難や予想外の壁が立ちはだかります。しかし、儒烏風亭らでん氏の体験談が示すように、それを乗り越えた先に、想像もしなかった素晴らしい未来が待っているかもしれません。この記事が、あなたの夢への一歩を踏み出す、ささやかな応援歌となれば幸いです。
引用元








