ホロライブ、それは多くの人々にとって夢の舞台です。きらびやかな衣装をまとい、多くのファンを魅了するVTuberとしての活動は、まさに憧れの的でしょう。しかし、その門は非常に狭く、合格を勝ち取ることは並大抵のことではありません。
今回、私たちはホロライブの人気メンバーである鷹嶺ルイさんの驚くべきオーディション体験談を深掘りし、そこから私たちが学べる「合格を引き寄せる秘訣」を探っていきます。一般的な社会人の視点から、彼女の言葉が持つ意味や、私たちの日常生活やキャリアにも応用できる教訓について考察します。夢に向かって努力するすべての皆様にとって、この記事が少しでも有益な情報となれば幸いです。(この記事はいち個人である私自身の考え、見解をまとめたものです。皆さんの一つのヒントになれば嬉しいです。)
鷹嶺ルイさんの「5回の挑戦」が示す諦めない心
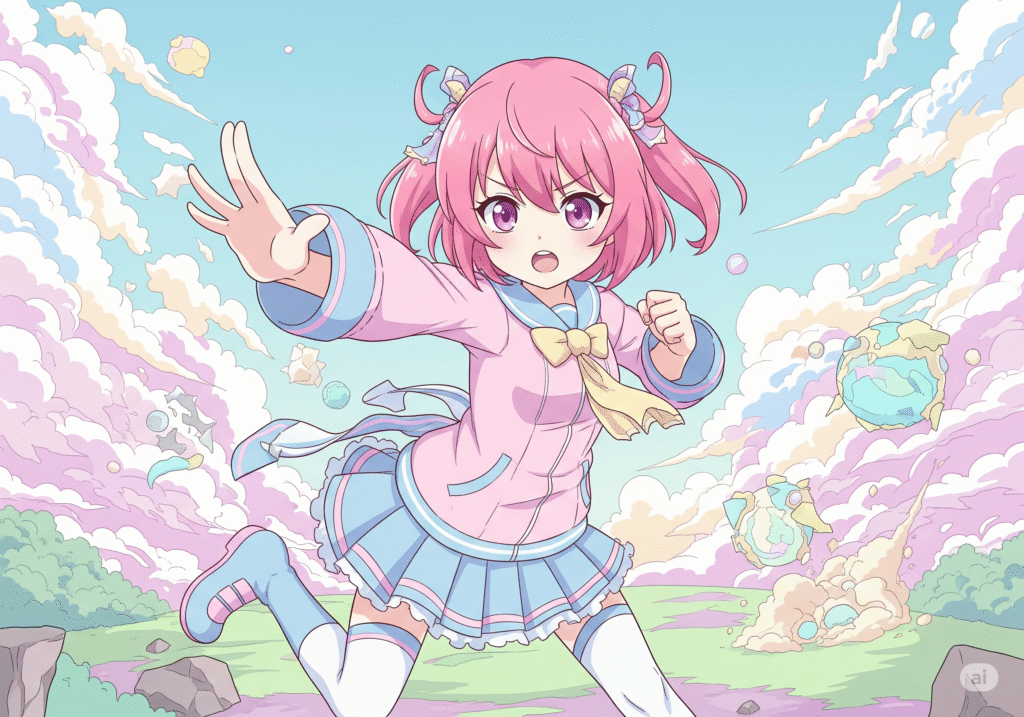
鷹嶺ルイさんのホロライブオーディションへの挑戦は、まさに「不屈の精神」を体現しています。彼女は、なんと5回ものオーディションに挑戦したと語っています。

『これね、もうね、OKもらったから話すけど、私ね、あのホロライブに入るために5回オーディションチャレンジしてるのよ。5回オーディション受けて、受かってるから、やっぱね、この場でなんか悲しいことだったりね、悔しいことがあっても前に進むことをね、辞めちゃいけないなって思っているんで、頑張りたいなと思いますね。』(原文ママ)
さらに、その回数についても、単純な5回ではない、という興味深い補足があります。



『ま5回というよりはなんか4.5回みたいな感じなんだけど。なんか4回目で結構あの見てもらえたから、あ、今だ!つって。今!今だ!今が私の売り込み時!って言って5回目を送ったらあの連絡が来たって感じかな。』(原文ママ)
一般の社会人として、この「5回(あるいは4.5回)の挑戦」という話を聞いて、まず感銘を受けるのはその圧倒的な粘り強さです。多くの人は、一度や二度失敗すれば諦めてしまうものです。特に、明確なフィードバックがない状況での不合格は、精神的に大きな打撃となります。しかし、鷹嶺ルイさんはそこで立ち止まらず、悔しさをバネに、次にどうすれば良いかを考え、行動し続けています。
これは、就職活動や資格取得、あるいは仕事でのプロジェクト推進など、あらゆる挑戦において非常に重要な姿勢です。一度の失敗で諦めるのではなく、何が悪かったのか、どう改善できるのかを常に問い直し、試行錯誤を繰り返すこと。このプロセスこそが、最終的な成功へと繋がる道を切り開くのです。彼女の言葉からは、単なる努力だけでなく、「夢を諦めない」という強い意志がひしひしと伝わってきます。これは、目標達成のために不可欠な心の在り方だと言えるでしょう。
書類審査突破の鍵は「見やすさ」にあり


オーディションの最初の関門は、多くの場合「書類審査」です。鷹嶺ルイさんは、この書類審査における重要な気づきを共有してくれました。最初の2、3回の応募では、送った動画がほとんど見てもらえなかったといいます。



『私オーディション5回受けてるんすよ。
2.3回送った時に動画も送るんだけど、オーディションて動画がこうあまり見られなかったから、何を書いたら見てくれるだろうみたいな感じで考えたタイミングがあって。
で、もっと見やすさを、そうこだわろうと思って、えっと3回目から見やすさをさ、あのフォームがあるんだけど、そのフォームってさダダダダだって書くと結構見づらいのよ。
カギカッコとか付けてさ、過剰書きとかにして見やすさをさ、求めてさ書いたりとかして、で4回目で動画が結構見られたの、見てもらえたのね。』(原文ママ)
この話は、非常に実践的な教訓を含んでいます。動画が見られないという状況に対し、鷹嶺ルイさんは「何を変えれば見てもらえるか」を深く考察し、「見やすさ」という点に辿り着きました。具体的には、応募フォームの書き方を工夫し、だらだらと書くのではなく、箇条書きや括弧を使うことで、情報を整理し、読み手が理解しやすい形にしたとのことです。その結果、4回目の応募で動画を見てもらえるようになったのです。
一般的な社会人の視点から見ると、これはビジネスにおける「プレゼンテーション能力」や「顧客視点」に直結する重要なスキルです。企画書、報告書、メール、そしてもちろんプレゼンテーション資料など、私たちは日々、自分の考えや情報を他者に伝える機会に恵まれています。その際、どれだけ内容が優れていても、それが「見やすく」「分かりやすく」なければ、相手に伝わらず、評価されない可能性があります。
鷹嶺ルイさんの経験は、「受け手のことを考えて、情報を整理し、伝わりやすい形にすること」の重要性を教えてくれます。これは、採用担当者や審査員といった「読み手」の時間を奪わず、効率的に情報を届けるための配慮であり、プロフェッショナルな姿勢の表れと言えるでしょう。単に「良いものを作った」で終わるのではなく、「どうすれば相手に伝わるか」までを考え抜くことが、次のステップに進むための鍵となるのです。
「2週間ルール」の謎と、戦略的「追撃」の重要性
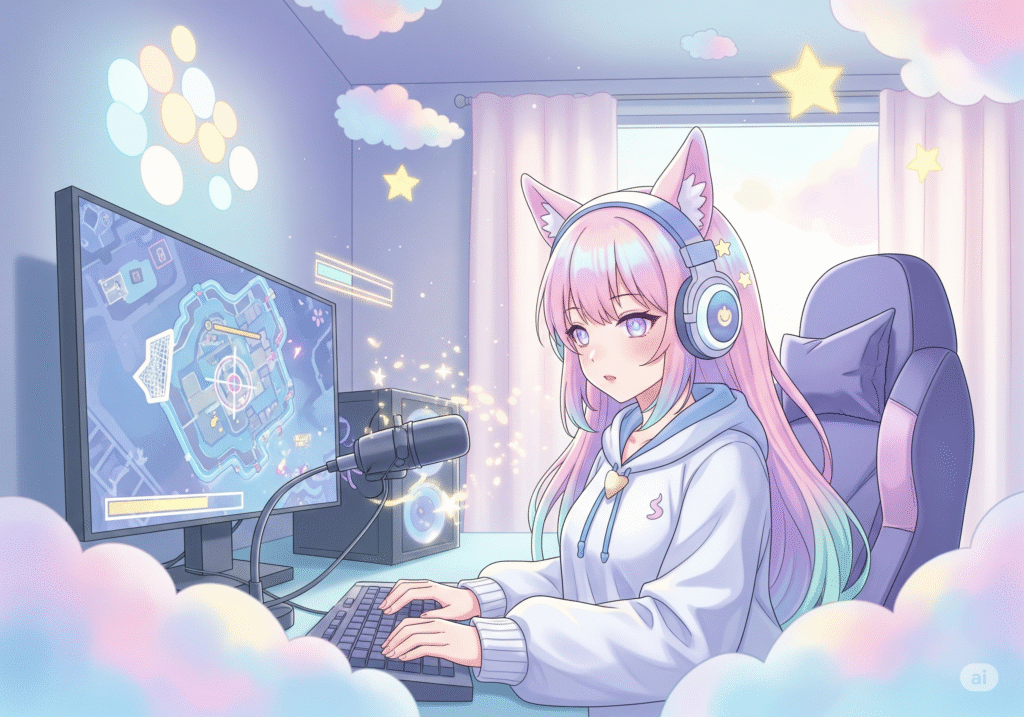
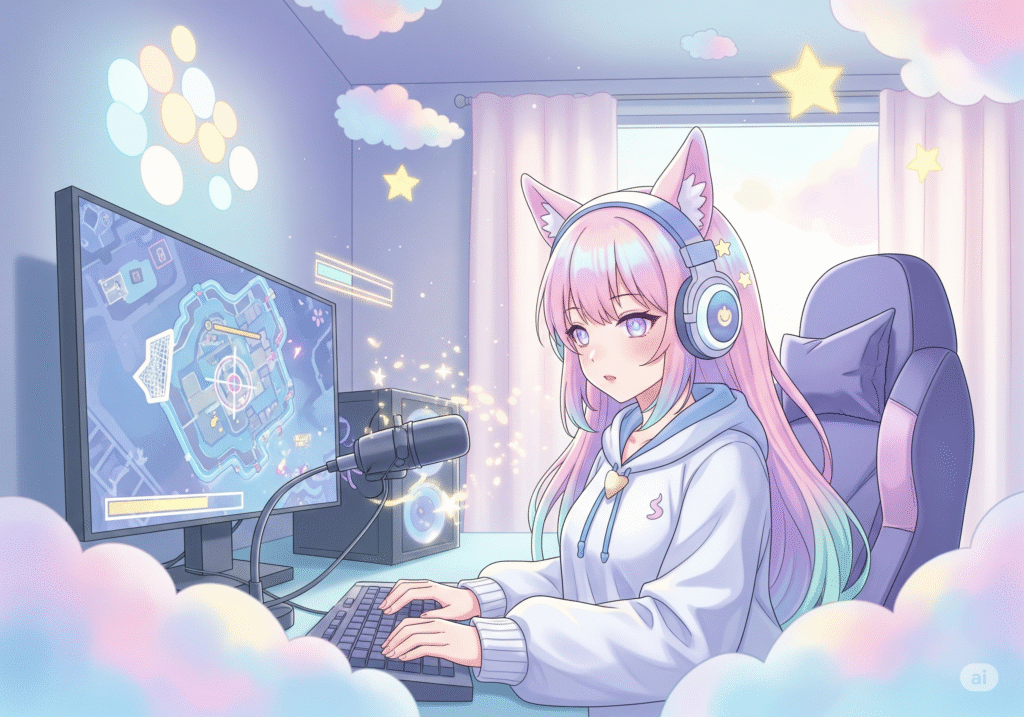
オーディションでは、合否の連絡期間にも注意を払う必要があります。鷹嶺ルイさんの経験では、動画を見てもらえた後、「2週間経って連絡が来なかったら落ちてます」という目安があったそうです。しかし、この「2週間」が営業日なのか、それとも通常の暦日なのかが不明確だったといいます。



『見てもらえたから、あれって2週間みたいなのがあるのよ。
2週間経って連絡が来なかったら落ちてますみたいな。
でさ、その2週間がさ、なんか営業日の2週間なのか分からなかったわけ。
営業日2週間なのか、通常の2週間なのか分からないのね。
だから、見られたと思ったその次の日が営業日ではなく普通に送った2週間後だったから、追撃で送れつって5回目を送って。
で、そしたらなんか次の日ぐらいに連絡が来たのね。』(原文ママ)
この状況に対し、鷹嶺ルイさんは「追撃」という非常に積極的な行動に出ました。4回目で動画が見てもらえたものの、その2週間が暦日で考えると連絡が来なかったため、「今が売り込み時」と判断し、5回目の応募をすぐさま送ったのです。すると、驚くべきことに、その翌日には面接の連絡が来たというのです。この結果から、彼女は「多分あれだよね、営業日だよねあれ」と振り返っています。
このエピソードは、社会人として「あいまいな情報」にどう対処し、「タイミング」をどう見極めるかという点で、非常に示唆に富んでいます。ビジネスの現場では、ルールや指示が明確でないことは珍しくありません。そのような時、ただ待つだけでなく、自ら状況を分析し、リスクを承知で次の手を打つ「主体性」と「決断力」が求められます。
鷹嶺ルイさんは、不確かな情報の中で「営業日」である可能性を推測し、絶好のタイミングを逃さないために、すぐに行動しました。これは、単なる運任せではなく、これまでの経験と状況判断に基づいた「戦略的思考」の賜物です。もし彼女が「2週間経ったからもうダメだ」と諦めていたら、ホロライブの門を叩くことはできなかったかもしれません。待つだけではなく、自らチャンスを作り出す積極性が、成功への道を切り開くことを教えてくれます。
タレント志望から裏方志望まで?情熱が生んだ「備考欄」の衝撃
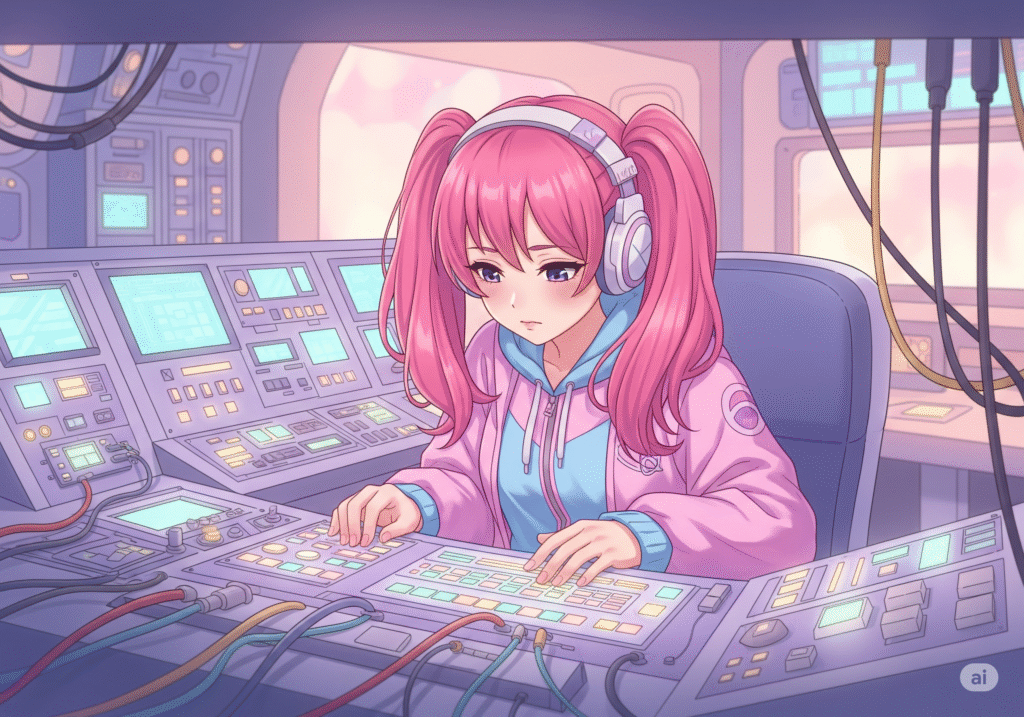
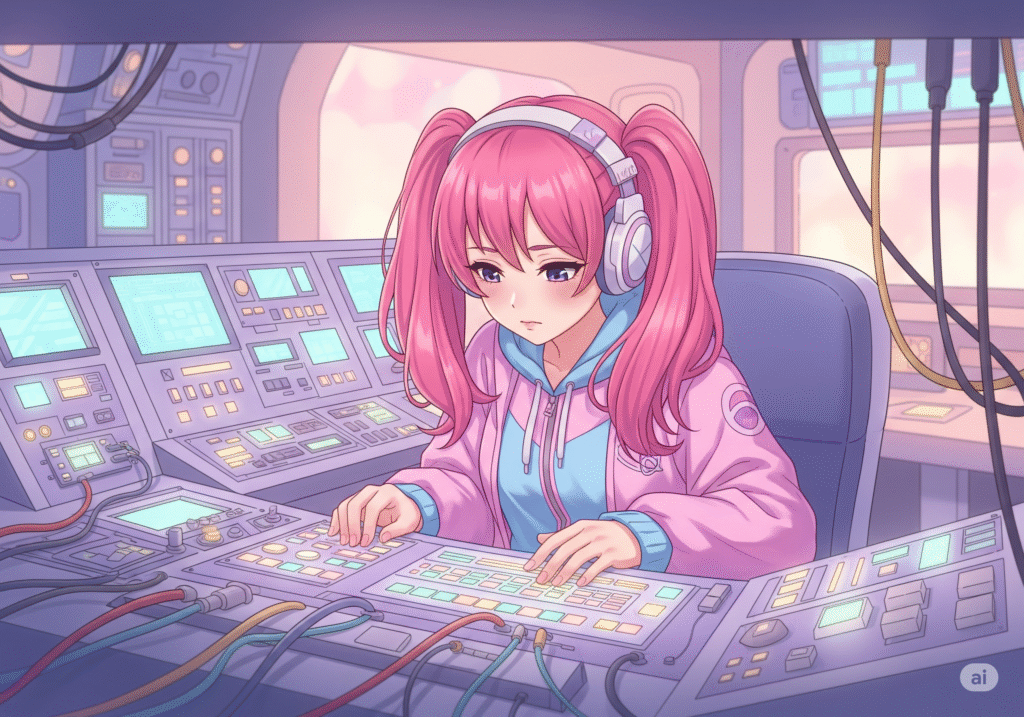
鷹嶺ルイさんのホロライブへの情熱は、その応募書類の「備考欄」にも現れていました。彼女は、5回目の挑戦で不合格だった場合、タレントとしての夢を諦める覚悟だったと述べています。しかし、それでもホロライブとの関わりを諦めきれず、驚くべき一文を書き添えていたのです。



『もう5回目で落ちたらタレントは諦めようって思ってたのね。
だから備考欄に、もしそのタレントとしてなんかちょっと魅力がないのであれば裏方やりたいですみたいな。
備考欄に書いてたわけよ。』(原文ママ)
この備考欄でのアピールは、面接の際にも話題になったといいます。



『1回目にさ、あのオーディションの人とまあのスタッフさんと話した時にさ、私はどちらで今先行されているのですか?って聞いたよね。
そしたら、いやタレント側ですよ安心してくださいって言われ、めちゃびっくりしてた。』(原文ママ)
彼女は元々、歌が好きでタレントとして活動したいという思いが一番にありながらも、企画や番組ディレクターのような裏方の仕事にも興味があったと語っています。
社会人としてこのエピソードを考察すると、これは「企業への深いコミットメント」と「柔軟な姿勢」を示す最高の事例だと感じます。多くの応募者は、自分がやりたいポジションや役割に固執しがちですが、鷹嶺ルイさんは「ホロライブという組織そのものに貢献したい」という、より大きな目標を持っていたことが伺えます。
「タレントとして魅力がないなら裏方でも」という一文は、単なる妥協ではなく、「どんな形であれ、この素晴らしい組織の一員となり、貢献したい」という純粋で強烈な情熱の表れです。採用側からすれば、このような人材は非常に魅力的でしょう。なぜなら、その人は自分の役割を超えて組織全体に貢献しようとする可能性を秘めているからです。これは、就職活動においても、企業が求める「入社後の貢献意欲」を最大限にアピールする、非常に効果的な方法と言えるでしょう。自分の希望だけでなく、企業が抱える課題や必要としている人材について深く考察し、それに対して自分ができることを提示する。この柔軟性と貢献意欲が、成功への扉を開く重要な要素となるのです。
なぜ「個人VTuber」ではなく「ホロライブ」だったのか?明確なビジョンの力


VTuberとして活動を始める道は、ホロライブのような大手事務所に所属するだけではありません。個人で活動する選択肢もあります。しかし、鷹嶺ルイさんは、なぜ個人での活動ではなく、ホロライブでのデビューを強く望んだのでしょうか。彼女は明確な理由を語っています。



『だってさ、もうその時にはさ、もう私がVtuberとして活動したいと思った時には、もうVtuberが溢れていて、
で、あとやっぱりホロライブを見てて、ホロライブの、こうライブだったりとか3Dだったりとか、2あのこうやってね、
こういう2Dだったりとか見て、やっぱすごい憧れもあっし、
もし叶うならやっぱりホロライブの皆と一緒にライブに立ちたいなと思ってたのきっかけっていうのはあるね。』(原文ママ)
さらに、個人で活動することの現実的な困難さも認識していました。



『個人のVtuberさんって本当にもうすごいんよ。
自分で全てを賄うわけじゃん。
で、すごいお金がかかるわけじゃん。
なんか、そこまでの、まあ財産も無かったから私には。』(原文ママ)
彼女は、もしホロライブに受からなかった場合の「もしもの話」として、親に土下座してでも個人VTuberになっていた可能性も否定しないほど、VTuberとしての活動に強い意欲を持っていました。
この鷹嶺ルイさんの話は、キャリアプランを考える上で非常に重要な視点を与えてくれます。彼女は、VTuber市場の現状(既に飽和状態であること)、ホロライブが提供する唯一無二の価値(ライブ、3D、2Dといった高いクオリティと、仲間と共にステージに立つ夢)、そして個人で活動する上での現実的な障壁(金銭的・運営的負担)を冷静に分析しています。
社会人として、このような「自己分析」と「市場分析」の重要性は言うまでもありません。自分が何をしたいのか(VTuberとして活動したい)、なぜその組織なのか(ホロライブで仲間と共にハイクオリティな活動をしたい)、そしてその組織でなければならない具体的な理由(個人では困難な資金面や技術面、そして共演の夢)が、非常に明確に言語化されています。これは、就職活動における「志望動機」の深さに直結します。単に「好きだから」ではなく、「なぜその場所でなければならないのか」を論理的に説明できることは、採用担当者に強い納得感を与えます。
また、「財産がなかった」という現実的な問題認識も、自己の強みと弱みを客観的に把握している証拠です。自分の限界を理解し、それを補うために最適な環境を選ぶという戦略的な思考は、ビジネスの世界でも大いに役立ちます。明確なビジョンと、それを実現するための現実的な戦略。これが、鷹嶺ルイさんが夢を掴んだ大きな要因の一つと言えるでしょう。
面接で「引かれた」まさかの回答、しかしそれが合格に繋がった理由
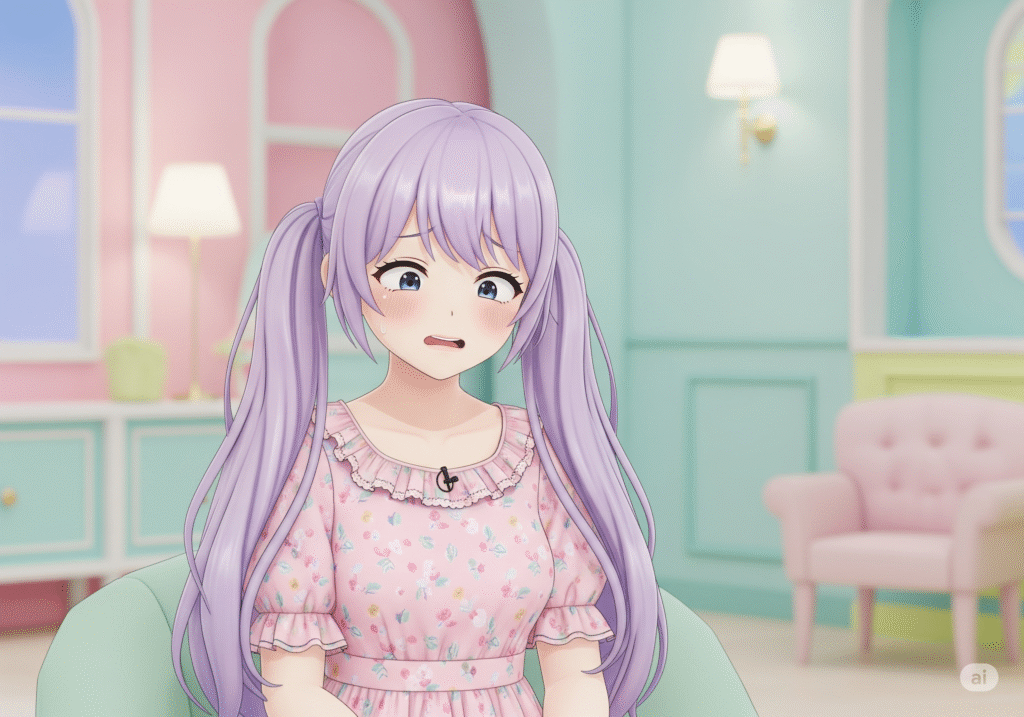
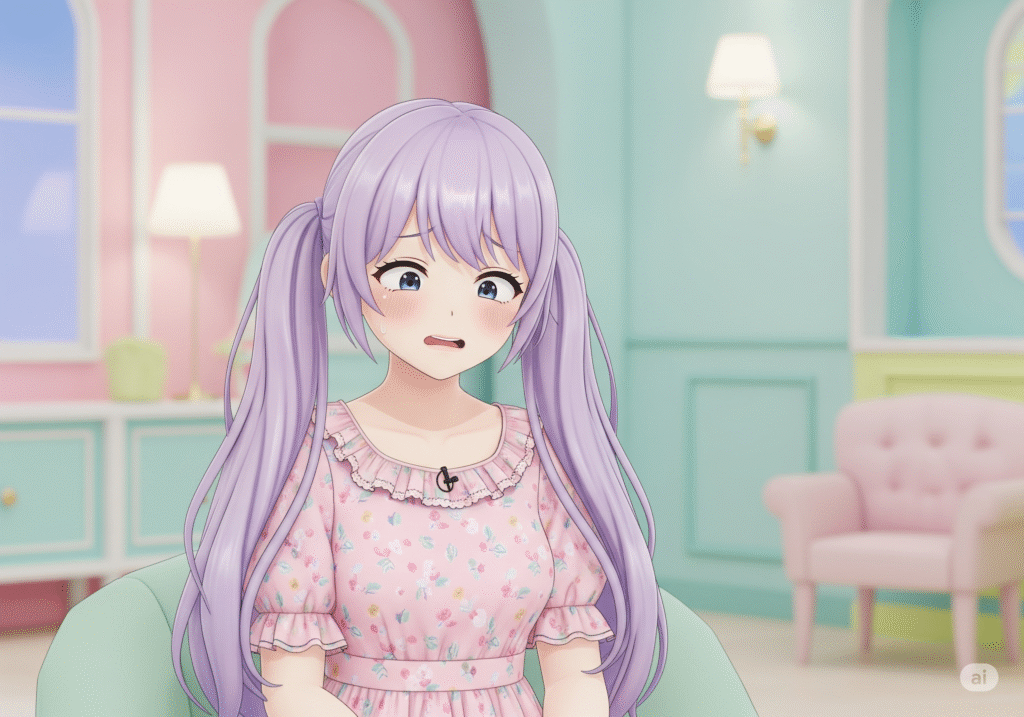
書類選考を突破し、いよいよ面接の場へ。鷹嶺ルイさんは、そこで面接官を「引かせて」しまった、と冗談交じりに振り返る一幕がありました。アンケート形式で提示された選択肢の中から、彼女が実際に何をしたかという問いに対し、正解は「ホロメン一人ひとりの尊敬しているところを語った」でした。



『書類が通って第1次面接の時に、
ルイさんが、尊敬しているホロメンて誰ですか?
みたいな話をした時に、0期生からずっとあの1人1人お話をしたんですね。
で大体あのあの2期生ぐらいの時に、これって全員やりますか?って言われて、
あ全員やるつもりですって言って、
あ、じゃあもう大丈夫ですって。』(原文ママ)
面接官に「もう大丈夫です」と言われるまで、0期生から順番にホロライブメンバー全員への尊敬の念を語り続けたというのです。この状況は、面接官が困惑したであろうことが容易に想像できます。しかし、驚くべきことに、彼女はこの面接を突破し、合格を勝ち取っています。



『引かれた引かれたとて、受かってんだから良かったですね。
はい、引かれて落ちてたらちょっと参考にしないでくださいだったんですけどね。
受かってました。ありがとうございます。
ちょっと困らせ、困らせちゃいましたね。』(原文ママ)
このエピソードは、社会人として非常に興味深い教訓を含んでいます。一見すると、面接官を「困らせた」行動が、なぜ合格に繋がったのでしょうか。それは、彼女の行動が「本物」の情熱と「深い知識」の表れだったからだと考えられます。
面接官は、多くの応募者を見ています。マニュアル通りの完璧な回答よりも、時として「その人らしさ」や「飛び抜けた情熱」が、強い印象を残すことがあります。鷹嶺ルイさんは、ホロライブへの愛情を建前ではなく、心の底から語りました。0期生から全員の名前と尊敬する点を挙げられるほどの深い知識と、それを語りつくそうとする熱意は、他の応募者とは一線を画すものであったはずです。
もちろん、これは「面接官を困らせれば良い」という話ではありません。重要なのは、自分の個性を隠さずに、情熱や知識を「本物」として示すことです。ビジネスの場でも、時に常識を打ち破るような熱意や、専門分野への深い洞察が、周囲を動かし、新たなチャンスを生み出すことがあります。彼女のこの経験は、小手先のテクニックではなく、真の情熱が人の心を動かす力を持つことを教えてくれる、素晴らしい事例だと言えるでしょう。
まとめ:あなたの夢をホロライブで叶えるために
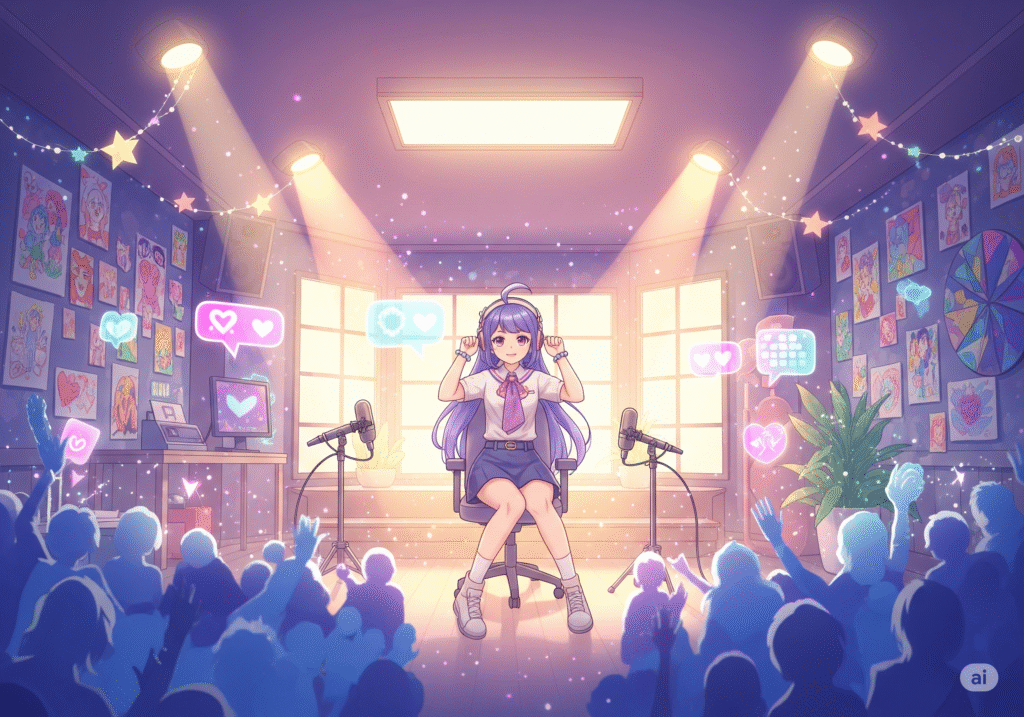
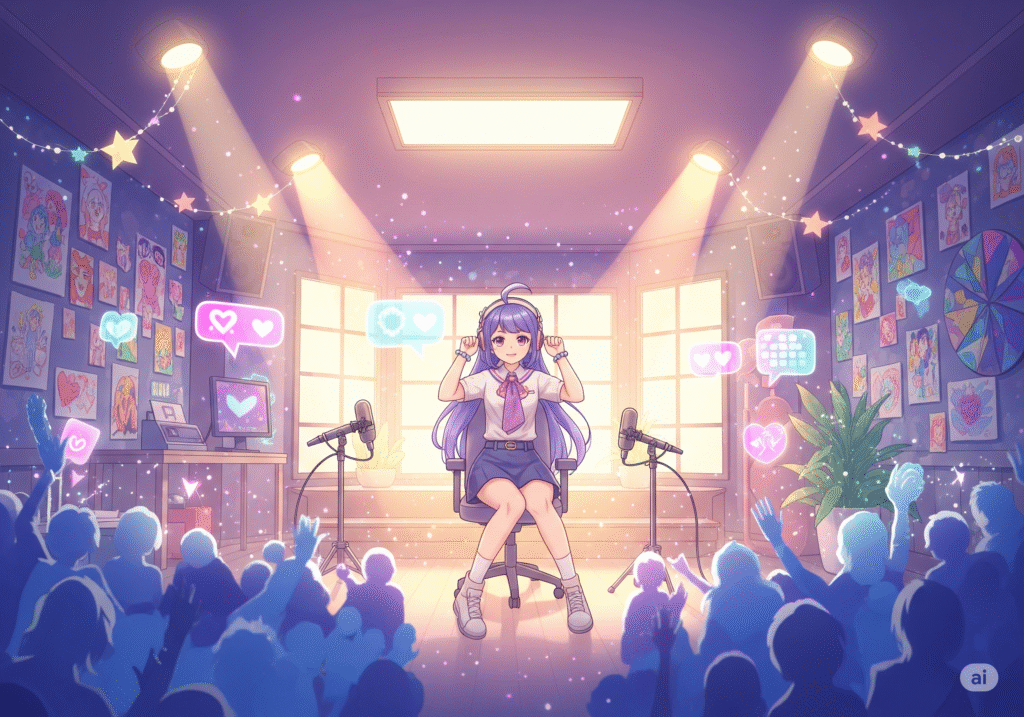
鷹嶺ルイさんのホロライブ合格への道のりは、私たちに多くの教訓を与えてくれます。彼女の体験談から、夢を掴むために不可欠な要素がいくつも見えてきました。
1. 「諦めない心」と「継続する力」: 5回もの挑戦は、目標達成のためには何があっても立ち止まらない、という強い意志と、改善を加えながら努力し続けることの重要性を示しています。
2. 「受け手視点」での工夫: 書類審査で「見やすさ」にこだわり、情報を整理して伝えることの重要性は、あらゆるコミュニケーションにおいて基本となるスキルです。
3. 「戦略的思考」と「主体的な行動」: 不明確な情報の中で最善のタイミングを見極め、自ら次の手を打つ「追撃」の姿勢は、チャンスを逃さないための知恵と勇気を与えてくれます。
4. 「組織への深いコミットメント」と「柔軟性」: たとえ希望する役割でなくても、組織に貢献したいという純粋な情熱は、採用担当者に強い印象を残します。備考欄に記されたその一文は、彼女の真のホロライブ愛の証でした。
5. 「明確なビジョン」と「現実的な分析」: なぜホロライブでなければならないのか、なぜ個人活動では難しいのかを深く考察し、論理的に説明できることは、自己理解と市場理解の深さを示します。
6. 「真の情熱」と「個性」のアピール: 面接で「引かれる」ほどにホロライブメンバーへの尊敬を語り尽くしたエピソードは、マニュアル通りではない、本物の情熱が人の心を動かすことを教えてくれます。
鷹嶺ルイさんは、



『書類に関しては、みんな、あの諦めずに何度も送ると、タイミング的に見てもらえたりとかする』(原文ママ)
と、ホロライブを目指す方々にエールを送っています。
彼女の道のりは、まるで難攻不落の城を攻略していくかのようでした。何度も跳ね返されながらも、諦めずに情報収集と分析を続け、戦略を練り、最終的には城門を開く鍵を見つけ出したのです。ホロライブという大きな夢に向かう皆様も、鷹嶺ルイさんのように、目の前の壁を乗り越えるたびに新たな知恵と力を得て、最後にはその輝かしい舞台に立つ日が来ることを心から応援しています。諦めなければ、道は必ず開かれます。
引用、参考資料チャンネル








